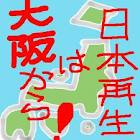大阪市長選で「橋下氏」が勝利して、はや10日。
連日、マスコミ報道を賑わせていますが、非常に興味深く見守っています。
2chにおいてもお祭り状態で、早くも「橋下首相」待望論が出ています。
何がここまで世間を盛り上げるのでしょうか?
これはひとえに、「既得権益」に対する嫉妬や妬みの類だと思われます。
どこかの報道で、「このような”民衆の負の感情”を利用することは危険です」
みたいなことを言っていましたが、「公務員を全てリストラしろ!」と言っている訳ではないので、
大阪市の職員の方々も、それほどビビる必要はないのでは??と思ってみています。
今、戦々恐々としている人達は、何らかの”やましさ”を持っているからだと思われます。
例えば、昨日の報道でもありましたが、公務員の採用試験無しでコネで登用されている方とか、
就業時間内に野球をやって遊んでいる人達でしょう。
橋下氏は、貢献度の高い、頑張っている、若手の公務員を切ることはしないはずです。
公務員改革といっても、公務員を一括りにすると話がおかしくなります。
まず、大阪市の公務員の大半は、政令指定都市の一般行政職ですから、彼らはエリートです。
予備校でも、道府県庁上級試験よりも難易度は高く、就職偏差値は非常に高いです。
現在の公務員試験は非常に難しく、相当努力した人でないと入れないでしょう。
だからといっては何ですが、優秀な人が多く、常識はずれな人は少ないはずです。
問題視されているのは、1万2千人程度いる“現業職員”の方々です。
先日、大阪市の職員が殺人未遂容疑で逮捕された事件がありましたが、その方も現業職員です。
現業職員とは、主に大卒未満の人が就く職業ですが、未だにコネ採用があります。
職種としては以下のような職種がありますが、実は非常に人気が高い職業です。
「清掃職員、駐輪場の管理人、給食調理員、学校の用務員、私鉄や市バスの運転手etc.」
これらの職種を侮ってはいけません。一生勤めると、定年間際には年収1000万の人が普通にいます。
そのため、過去には学歴を逆に偽って応募する人もいたようです。
それが表沙汰になったのは2007年だったと思いますが、大阪市は全庁的に学歴調査をしました。
すると、出るわ出るわ「逆・学歴詐称」のオンパレードで、最終的には400名以上が自首したようです。
しかし、大阪市はこれらの学歴詐称者達を、懲戒免職にはしませんでした。
その理由が、「すでに何年間も働いている人の安定した生活を奪うのは厳し過ぎる」とのことです。
ちなみに、尼崎市で同様の事件が発覚した際は「即・懲戒免職」になりました。
こうした点からも、いかに大阪市の対応が甘いか分かります。
昨日、その大阪市の職員に対して、橋下氏は凄いことを指示しました。
「現業職員の採用経緯を明らかにして報告して欲しい」
「問題あれば、再試験を課す」
これはしびれます。
今まで誰も切り込まなかったところに、手を付けるなんて素晴らしいの一言です。
この際、徹底的にやっていただきたいと思います。
そういえば、先日、鎌倉市役所の駐車場に車を止めたのですが、
たった83台の駐車場に管理職員のオジサンが10名程いました。(年齢的には60歳以上)
しかも、態度が横柄。陰でタバコ吸っている等、マナーが悪い。。。。
「なんじゃこりゃ?」って感じです。
わたしは鎌倉市の納税者ではないので文句は言えませんが、よく市民から苦情がこないなと思いました。
これらは「一事が万事」であり、おそらく、このような無駄遣いは様々なところにあるのだと思います。
市町村が管理する施設において、雇用を生むことは重要だと思いますが、
その際は、是非、若い人に職を渡して欲しいと思います。
大阪市が浄化されれば、今後は日本全国の政令指定都市、さらには都道府県や国にも流れは拡がるでしょう。
橋下大阪市長には、是非とも頑張ってもらいたい!と思う今日この頃です。